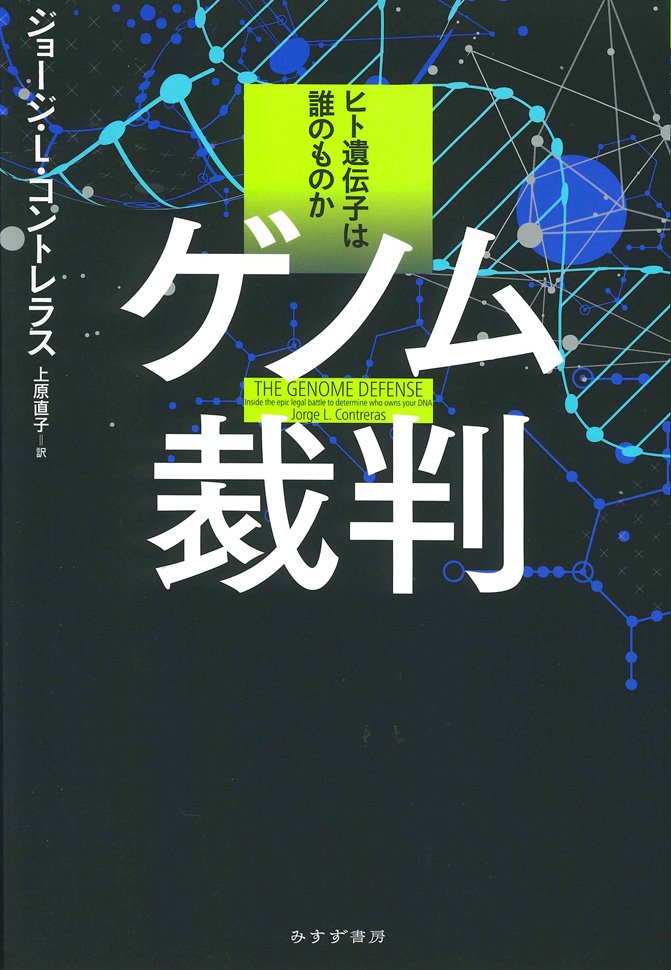米国最高裁判決AMP v. Myriad事件(569 U.S. 576, 2013)は、他の3最高裁判決(Bilski事件561 U.S. 593(2010), Mayo事件566 U.S. 66(2012), Alice事件573 U.S. 208(2014))と共に、特許保護適格性につき、それまで米国において30年以上確立されていた判例法理を覆し保護対象を狭めた判決として著名である。本判決は、AMP(分子病理学会)や臨床遺伝学者、個人のがん患者等20組の原告を、有名な人権擁護団体であるACLU(American Civil Liberties Union, アメリカ自由人権協会)がまとめ、Myriad社の遺伝子特許の無効を求めて提訴したものである。特許権侵害訴訟ではなく、ヒト遺伝子の特許化という概念自体への異議申立てである点で、異色の訴訟であった。本書は、ユタ大学法学教授の著者が、本件に関与した弁護士、当事者、判事、政府職員、患者など100人以上に、判決直後から7年間にわたって対面インタビューをし、膨大な訴訟記録、関連論文等も駆使して描き出した本件訴訟の壮大な全貌である。私もこの訴訟を論文で取り上げてきたが、その背景に、これほどの多くの人間ドラマが織り成されていたことを本書により初めて知り、言い知れぬ感動を覚えた。ACLUのまだ若い初代科学顧問が、ヒト遺伝子に特許が認められるのはおかしいと感じ、人権が専門の弁護士がこれに賛同したことが発端であったが、著者も巻末の解説で述べている通り、Myriad社の特許は、ヒトの体内に存在する遺伝子に対してではなく、あくまでも単離精製されたDNAに対して認められたものである。この点で、発端となっていた疑問は法的に正確ではなく、実際、彼らが相談した特許専門家は、誰も理解しなかったという。しかし、そのような批判をものともせず、Myriad社から乳がん遺伝子検査の差止警告を受けた大学病院の研究者や、高額なMyriad社の検査を受けられない女性など、この特許権に起因する被害を受けている多様な人々をコツコツと集め、チームを作って不可能に見える訴訟に挑んでいく様子、世論を動かし、最高裁の前に政治活動とは無縁な女性たちのデモができるまでの描写、そして、最高裁判事との議論の活写は、気迫に満ち、ぐいぐいと引き込まれた。¶001
参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
井関涼子「ジョージ・L・コントレラス著、上原直子訳『ゲノム裁判――ヒト遺伝子は誰のものか』」ジュリスト1602号(2024年)106頁(YOLJ-J1602106)