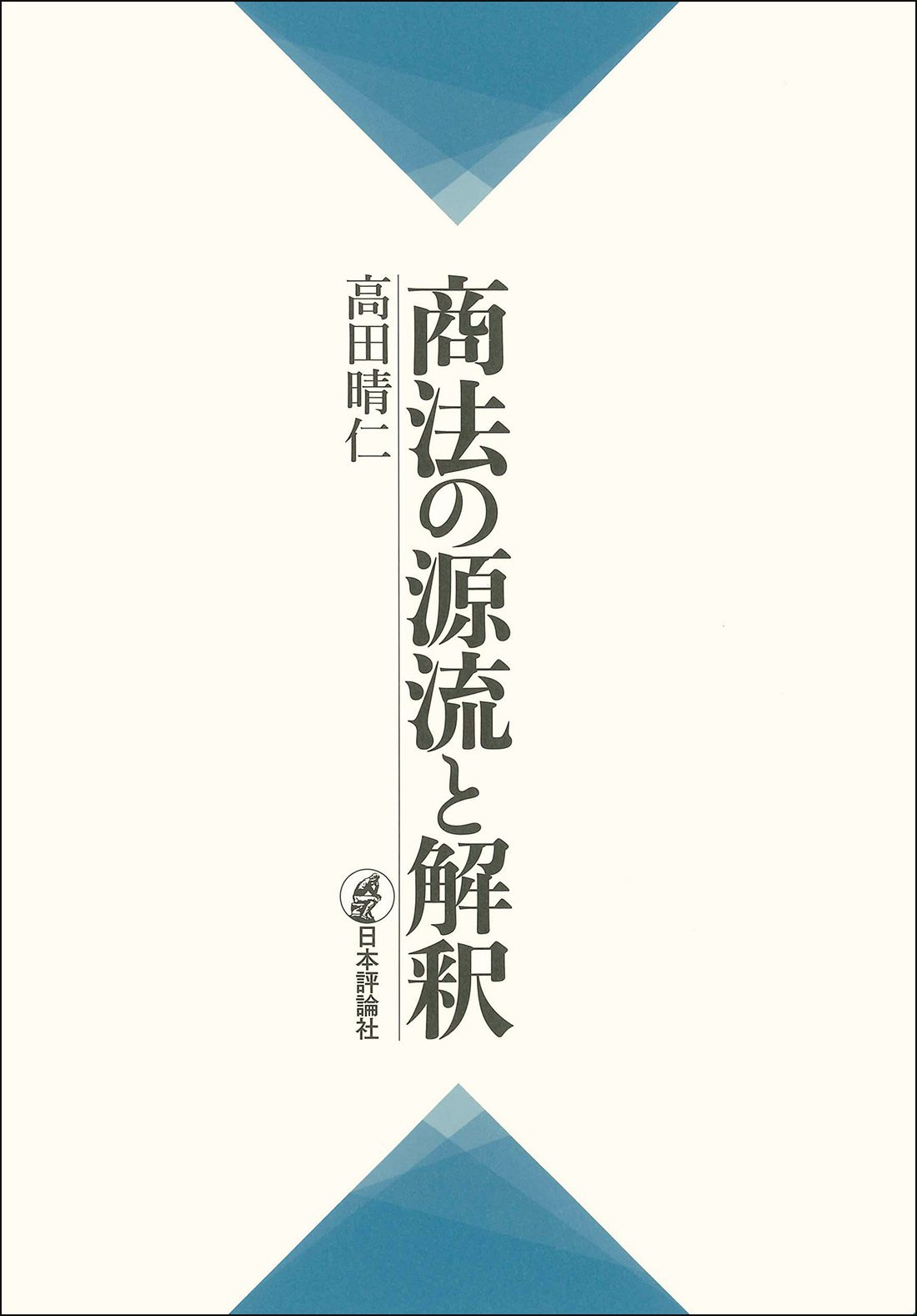参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
本書は、著者が1998年から2016年までに公表してきた16編の論説を集めた論文集である。論文集と言っても、書名にも現れているとおり、そこには商法の法制史的な視点という一貫したテーマが存在している。¶001
これまでの商法分野における法制史的研究と言えば、明治32年の現行商法の成立過程を中心としたものが多い。それに対して、本書は、これまでの先行研究があまり着眼しなかった点を対象としている。具体的には、第1編ではロェスレル草案の起草から明治23年の旧商法の制定までを扱い、第2編ではその旧商法の施行をめぐる商法典論争を扱っている。もっとも、本書も現行商法の成立過程も扱っているが、第3編で焦点を当てているのは、日本民法典の父とされる梅謙次郎の商法学者としての一面である。続く第4編は、最近の法改正を契機に変化が生じた「社団」性及び株主による差止請求制度について、法制史的な面から新たな意義を検討している。最後の第5編は、本書の中でも最多の5本の論文が収められており、そこではロェスレル草案が現在の我が国におけるコーポレートガバナンスに影響を与えていることを明らかにしている。¶002
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
三宅新「高田晴仁著『商法の源流と解釈』」ジュリスト1578号(2022年)81頁(YOLJ-J1578081)